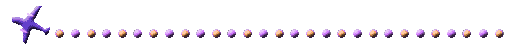
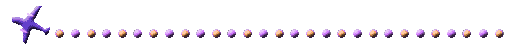
スマトラ旅行記
4日め(1月1日)
「商人の町、ブキティンギ」(ブキティンギ)
朝、10時前、乗り合いの小型バンでペカンバルーを後にしました。 バスと比べて値段も高いので、客筋もそれなりに立派です。ブキティンギまで14,000ルビア(約630円)というのは、ここではそれなりのお金なのでしょう。
ブキティンギまでの道のりは、目に跳び込んでくる景色が起伏に富んでいて、快適です。バタムからペカンバルーまでの過酷で単調な旅が嘘のよう。 水田や、水牛や、小綺麗な農家を見ていると、原生林ばかりの単調な景色でうんざりしていた一昨日とは大違い。
途中、高地にさしかかると、道を行くオートバイの量が急に増えていきました。スマトラの峠族なのです。 このあたり、オートバイ好きなら攻めてみたくなるような峠が延々と続きます。
午後2時、峠のなかほどで、昼食のため途中休憩。峠の茶屋という風情のドライブ・インに入りました。 ここで、初めて、パダン料理に挑戦しました。ジャカルタやジョグジャで、その光景は何度も見てはいたのです。 テーブルの上に、調理済みの皿がいくつも並び、客は好きなものを、好きなだけ食べる。勘定は食べた分だけ、という合理的なシステムなのですが、 見てくれの悪さや、手で食べるという点にひっかかっていて、一度も体験したことがありません。
ここでは選択の余地がないし、なにより空腹なので、迷わず手を出しました。料理は予想外のうまさで、カレー味のアヤム・ゴレン(揚げた鶏肉)が特においしい。 いちばん心配していた御飯も、暖かくて臭みがありません。水の替わりに、お湯がでたのもありがたかった。 「生水かもしれない」と心配しながら飲む水は、けっして、喉の渇きを癒してはくれないのです。
5,000ルピア(約225円)で初めて食べたパダン料理は、病みつきになってしまうような旨さでした。
空腹が癒されると、幸福な気分が戻ってきました。再び旅は続きます。このあたりから、徐々にミナンカバウ・スタイルの家が多くなってきます。 屋根が、水牛の角のように、天に向かって高く伸びている。 そもそも、ミナンカバウとは、「勝利の水牛」という意味だとか。 水牛が、ミナンカバウ族にとって、どれだけ大きな意味を持っているのか、この家々を見れば、よくわかります。
隣に座っていたお婆さんと、少しずつ打ち解けて、話がはずみました。日本語プラス英語vs.インドネシア語で、ほとんど通じ合わないのに、なぜか会話になってしまう。 言葉は通じなくても、気持ちだけは通じ合うというのが、袖すりあうも多生の縁、ということなのでしょう。
午後3時40分、約6時間の旅を終え、ブキティンギに着きました。運転手に「どこのホテルか?」と聞かれ、なにも考えていなかったことに気づきました。 ロンリー・プラネットで、たまたま覚えていた「ダイメンズ・ホテル」の名前を言ってみました。古くからあるホテルということで、これなら、運転手もわかるでしょう。
チェック・インして、すぐに街に飛び出しました。ブキティンギは高原の小さな街で、軽井沢を思わせます。 中心は、丘の上の時計台で、この時計台の周りから丘の下まで、小さな商店が、露天商も含めて、ぎっしりと密集しています。 つまり、街の中心は、すべてマーケット・プレースなのです。
ミナンカバウを形容するとき、必ず商売上手という言葉が出てくるのですが、この光景を見れば、なるほどとうなずけてしまう。
ブキティンギのマーケット(左)とオプレットの乗客(右)
この街の移動手段は、オプレット(小型の乗り合いバス)と馬車。 馬車が、観光用ではなく、日常の足として、完璧に機能しています。これは、西スマトラでは共通のことだと、徐々にわかっていくのですが。
ひととおり時計台の周りを歩いてから、ブキティンギの銀座通り、アーマッド・ヤニ通りに向かい、モナリザ・レストランで中華料理の夕食をとりました(5,000ルピア、約225円)。 中国人経営のレストランなのですが、味が現地化しています。
ブキティンギの中心、時計台
ジャラン・ジャランでホテルへ帰ると、急に疲れが出てきました。 前夜はほとんど寝ていないのです。大晦日の大騒ぎと、旅の疲れがどっと出て、早々と床に着きました。
1日め 2日め・その1 2日め・その2 3日め・その1 3日め・その2 4日め(you are here!) 5日め・その1 5日め・その2 6日め・その1 6日め・その2
7日め index
 トップ |
