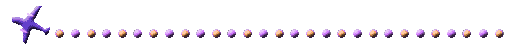
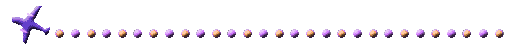
パタニ・異境の街
第2章
バンコクから南へ1055km下ったところにパタニの街があります。 最近の考古学上の発見から、かつては仏教王国が存在していたことが推定されているのですが、パタニという街の名前自体は、 マラッカ王国の支配下にあり、この街を強力に統治していたイスラム教のサルタンの名前から来ています。 17世紀には、東南アジアのイスラム学のセンターとして寄与する一方、中国と東南アジアを結ぶ貿易港としても大きな役割を果たすようになりました。
19世紀後半まで、パタニは、独立し、繁栄したイスラム国家でした。 20世紀に入ってタイに編入されたのは、タイとイギリスの政治上の綱引きの結果です。 しかし、どちらにしても、ふたつの文化がひとつの社会の中で混在している以上、そこになんらかの摩擦は生じていたのでしょう。 シンガポールでも、マレーシアでも、イスラム教徒と仏教徒、つまり中国系の住民とは、かつて、深刻な民族対立を引き起こし、社会に大きな亀裂を残しました。 インドネシアでは、いまだに中国人が人種暴動の標的とされています。
パタニの街を歩いていると、タイ文字に混じって、ジャヴィ語の文字を頻繁に見かけます。 アラビア文字に酷似したジャヴィ語のアルファベットは、マレーシア東海岸の街、コタバルでも見かけたのですが、 保守的なマレー系イスラム教徒の原理主義的な側面が感じられて、興味をかき立てられました。 インドネシアのジャワや西スマトラ、そしてリアウでは、けっして見かけることのなかったものです。
イスラム色の濃いパタニの街
スマトラのリアウ州も、マラッカ海峡を挟んだ対岸の国、マレーシアも、どちらもマレー人の土地なのですが、 インドネシアのマレー人と比べて、マレーシアのマレー人が、より原理主義的傾向が強いのは、とても不思議なことに思えます。 飲酒をし、煙草を吸い、婚外性交にも比較的リベラルなインドネシアのイスラム教徒と、息苦しいくらいに禁欲的なマレーシアのイスラム教徒との間には、 同じような歴史、文化を共有してきた同一民族とは思えないくらいの乖離があります。
シンガポール滞在中に、英字新聞「ストレイツ・タイムズ」で、マレーシアのマハティール首相関連の記事を読みました。 折しも日本滞在中のマハティールが、「イスラムも時代に合わせて変わっていかなければいけない。」と語ったという記事でした。
「例えば、偶像崇拝を厳しく禁じるイスラムは、肖像画の製作さえ禁じているが、写真が一般的になっている現代で、この規定は意味を失っているのではないか。」 という趣旨の発言をマハティールはしていたのですが、確かに、写真好きのインドネシア人と比べて、マレーシアのマレー人は、極端に写真を嫌がります。 写真に対する嫌悪感が、イスラム教の偶像崇拝の禁止から来ていることを知り、あらためて、文化の不思議さに驚愕したのでした。
第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章
 トップ |
