【潮州】
汕頭(すわとう)最後の日、朝から潮州の街へ行きました。汕頭の街外れからミニバスに乗り、およそ1時間。こぎれいで、こじんまりとした古い街並みは、経済特区の街として急速に発展し、荒々しい港町としての貌ものぞかせる汕頭とは対照的な趣があります。
この街の見所は、由緒ある仏教寺院の開元寺と、開元寺から西湖に至るまでの、壁に囲まれた、古い、いかにも中国的な街並みでしょうか。
開元寺は、玄宋皇帝の治世、開元26年(AD738年)に建立された、潮州で最大の仏教寺院。寺の前には、典型的な門前市の光景が拡がり、細い道の両側には、土産物やお参りセットを売る店が軒を並べています。僕も線香を買い求め、お寺の中へ入って行きました。
 開元寺前の門前町
開元寺前の門前町
寺そのものは、京都や鎌倉のものとほとんど大差はありません。少なくとも、素人が見ている限りは。本堂に掲げられた木屋架には、「開元鎮國禅寺」と表記されています。鎌倉あたりの禅寺の、侘び寂びを感じさせると思うのは、多分素人の後解釈でしょう。
寺の境内は、平日だというのに、なかなかの賑わいで、文革の後遺症は窺うことができません。一人の現人神が、古い信仰を根こそぎ抹殺しようとしたその凄まじいエネルギーが、人々の心にどれだけの傷跡を残したのか、いまではもう書物の中でしか知ることができないのですが、近代中国の歴史の業の深さというものが、それでも少しは落ち着いてきたなと感じさせてくれる光景ではありました。
 文革は遥か昔のことのようですが、人々の心に残した傷は癒えたのでしょうか。
文革は遥か昔のことのようですが、人々の心に残した傷は癒えたのでしょうか。
【潮州の街並み】
お参りの後は、のんびり街の中を歩きました。潮州はとても小さな街なので、散歩しながら、街の概要を知ることができます。
開元寺から、その北西にある西湖公園までが、この街のいちばんオリジナルな部分でしょうか。表通りには、2階建ての棟割長屋が連なっていて、騎楼造りの回廊に面した1階は、ショップハウスの店舗が並んでいます。裏通りは、細い路地が迷路のようにはり巡り、白い漆喰で表面を塗り固めた石の壁が、その中に拡がる長屋建ての住宅街を守っています。「城市」という言葉が、その実態を表しているかのようです。
 古い街並みがそのまま残る潮州の城市。
古い街並みがそのまま残る潮州の城市。
天秤棒をかついだ物売りが、物憂げな声を挙げながら、あちこちの路地を練り歩き、家々の軒下からは、洗濯物が路上にまではみ出していて、犬もあくびをかみ殺すような、平和で牧歌的な昼下がり。路地を囲む石の壁には、ところどころに門があり、中を覗きこむと、健全で、伝統的な地域社会の息づかいを、肌で感じ取ることができます。肩を寄せ合い、助け合いながら生きていく伝統的なアジアの地域社会のあり方が、ここでは、原型のまま残っているようでした。
 時はゆったりと流れているよう。
時はゆったりと流れているよう。
汕頭に帰り、ホテルの部屋で荷造りを始めていると、嵐のようなにわか雨。(つづく)
  
|
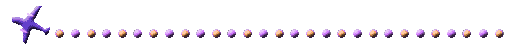
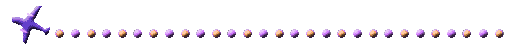
![]()