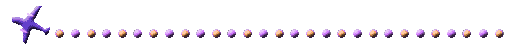
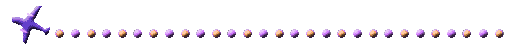
![]()
第3章 タイ
58
退屈な市内のドライブがしばらく続くと、女たちは荷物の中からランチ・ボックスを取り出した。炊きたての白米とフライド・チキンが、別々のビニール袋に入っている。車の中で朝食をとっている間、女たちはかしましい。信也も、スワンニーの勧めで、フライド・チキンに手を伸ばす。
食事をしながら、スワンニーは、彼女たちのプロジェクトについて、信也に説明をした。ペラク村に電気と水道を敷設するために、長い間、県に働きかけてきたこと、計画がほぼ確定し、県知事の視察が実現したこと、しかしそれは彼女の計画のほんの第一歩で、その後には、大規模な観光開発のプロジェクトが控えていること、イスラム教徒相手のビジネスがいかにやりにくいかといったことなどを、フライド・チキンをほおばりながら、淡々と話す。
車は、ハジャイ市内を出て、南東に向かう。市内から遠ざかるに連れて、人の住む気配が徐々に薄らいで行く。道の両側に連なる山々は、熱帯雨林を思わせるジャングルだ。ここは、もうすでに、マレー半島なのだ。
食事を終えたスワンニーは、信也にもたれかかるようにして、軽い居眠りをしている。世界に対するあらゆる警戒心を解いた表情は、無邪気そのもので、信也は、ふと、シェイクスビアの古い詩歌の一節を思い出した。
君を夏の日にたとえても
君はもっと美しいもっとおだやかだ
手荒い風は五月の蕾をふるわし
また夏の季節はあまりにも短い命。
時には天の眼はあまりにも暑く照る
幾度かその黄金の顔色は暗くなる
美しいものはいつかは衰える
偶然と自然のうつりかわりに美がはぎとられる。
だが君の永遠の夏は色あせることがない
君の美は失くなることがない
学生の頃、英文学の講義で読まされたソネット第18番の一節なのだが、正面から美を讃える一点の曇りのない力強さに、信也は不思議な感動を覚えたのだった。そして数年後、自分が衷心から求める女の横顔を見ながら、この詩を思い出したのだ。
一時間ほどで、車は山岳地帯を抜けた。カーブを曲がると、ときおり、生い茂った樹木の間から、陽光に輝くタイ湾のさざ波が見えてくる。山羊が道を横切り、小学生の女の子が、弟や妹を乗せて、スーパーカブを運転している。タイの田舎の、どこにでもある風景が、信也の視界に跳び込んでくる。
やがて、女たちを乗せたワゴン車は、県道をはずれて、未舗装の細道に入って行った。車の揺れでスワンニーは、目を覚ました。
「もうそろそろよ。」
後部座席の女たちも、そわそわとし始める。やがて、信也の目の前に、マレー人の集落が出現した。高床式の藁葺き屋根の家々で、竹を編んでできた壁は通風を優先して、ところどころにぽっかりと大きな隙間があいている。床の下には、農機具や、魚網や、ロング・テイルのボートが収納されている。水牛を飼っているのは、裕福な家なのだろう。はた目にも、普請の良さがうかがえる。
信也たちは、村の広場で車を降りた。村長らしい男とその取り巻きが、彼女たちを出迎える。和気あいあいとした雰囲気で、お互いの間に、根深い民族対立や宗教紛争などがあるとは思えない。
スワンニーは、信也を村長に紹介した。信也は、タイ式に胸の前で合掌したが、相手の男は、ただ、右手を差し伸べた。
スワンニーと村長は、そのまま、広場に面した新築の建物に向かった。近代的な、二階建ての建物で、明らかに民家ではない。
「この村のコミュニティ・センターで、私たちの募金で作ったのよ。」
スワンニーがささやいた。
女たちは、建物の中に入ると、そのまま二階に昇って行った。間仕切りのない、がらんとした部屋に、木彫りの民芸品や、バティック(ろうけつ染め)が陳列されている。民芸品は、タイのあちこちのナイト・マーケットで売っている安手の土産物程度だが、バティックについては、なかなかのできばえだった。
元来、バティックはインドネシアやマレーシアの特産品で、特にインドネシアのバティックは、国際的な評価も高く、芸術の域に達したものもある。
「みんな、この村で作ったのかい?」
「そういうことにしているの。」
スワンニーは笑いながら答えた。
「技術的にはまだ未熟で、製品の全部が全部市場に出せるというわけではないの。でも、このまま、半農半漁の生活を続けていても、村人たちに将来はないのよ。
いろいろな点で、もう少し、自助努力をしてくれたらと、思うことがあるわ。利益になれば、とても柔順になるけど、代償を払おうとはしないのよ。いざとなると、『これはあなたがたのビジネで、私たちのではない。』という言いかたをするの。」
「分離独立を求めているのかい?」
「ある人たちはね。たいていの人は、それがいかに非現実的かということがわかっているのだけど。」
「この村の中にも、分離独立運動にかかわっている者がいるのかい?」
「多分ね。この村は、もう、パタニ県に接していて、パタニは、イスラム教徒が圧倒的に多数を占めている南部四県のひとつなのよ。タイ政府のコントロールの及びにくい地域で、それだけテロ活動もさかんなところだわ。」
「平和そうに見えるけど。村長も柔順そうだし。」
「電気が来るからよ。電気が来れば、テレビも見れるし、冷蔵庫も買えるじゃない。そのためには、村の近代化に真剣に取り組んでいる姿勢を知事に見せる必要があるのよ。電気が来れば村長の威信は高まるし、失敗すれば面目丸潰れ。村人たちのテレビへの夢がまた遠のくわ。」
「で、見込みは?」
「大丈夫。話はできているの。知事の視察は、セレモニーね。」
「イスラム教徒のために、なんで君が熱心になるんだい?」
「開発よ。開発のためには彼らとの関係が大切だわ。それに、電気が来なければ、道路工事ひとつできやしない。」
「結局、電気が欲しいのは君なんだ。」
「違うわ。電気は誰にとっても必要なのよ。それが文明というものだわ。私が彼らを利用しているのだとしたら、彼らも私を利用しているの。でも、それは、悪いことじゃい。」
信也はなにも言わずに、一枚のバティックを手にとった。マレーシアのコタバルあたりの産だろうか。インドネシアのバティックから比べると、ずっと素朴で古典的だ。
「村の中を見たいのなら、誰かに案内させるわよ。私は、知事が来るまで忙しくて、あなたの相手はできないの。」
「わかってる。邪魔するつもりはないよ。」
スワンニーは、傍らの村長になにか伝えた。村の長老という言葉そのままの男で、スワンニーの言葉におおげさにうなづくと、信也を連れて階下に降りて行った。
広場の一角では、スワンニーの仲間の女たちが、村人といっしょになって、テントを立てている。祭りの準備をしているような雰囲気だ。村長は、村人の中から一人の少女を呼び付けた。
村長と少女は、ジャウィ語と呼ばれる独特の言葉で話している。マレー語の一種なのだが、マレーシアのマレー語とは明らかに違う。
ディアナという少女は、スワンニーのホテルで働いていた経験があるらしい。そのとき、習い覚えた片言の英語で、信也に挨拶をする。村で唯一、英語を話す人物なのだ。
信也は、ディアナの案内で村の中を歩き始めた。全部で五〇戸ほどの小さな村なのだが、それでも、よく見れば、豊かな家、貧しい家の区別がわかる。ディアナは、初心者程度の英語で、信也のガイドをつとめている。
男たちの大半は海に出て、残された年寄りや女たちが畑を耕す。最近は、彼女自身のように、パタニやハジャイの街に出て、現金収入を求める娘たちもいる。
生活はけっして楽ではないだろう。漁の成果の大半は、タイ人や中国人の網元のもとへ収まり、村人たちが手にする現金は僅かなものだ。
英語の語彙が少ないせいか、マレー人の少女は寡黙だった。寡黙なのは、少女だけでない。信也を見つめる村人たちの表情も、暖かいものではない。村の中を歩いていると、洗濯をしている女たちも、魚網の修理を手伝っている子供たちも、手を休めて、信也を凝視する。貧しいが、つつましく暮らしている人々の生活の場に、興味本位の外国人が土足で踏みこんでいるのだ。歓迎されるとは思っていない。
しかし、一方で、信也は、タイ東北部の寒村を取材で訪れたときのことを思い出した。行く先々で、村人たちは、見知らぬ異邦人である彼を歓迎したのだ。初めて見る日本人が珍しかったのだろう。豊かな家庭では、彼を呼びとめ、貴重な水を振る舞ってくれた。水道もなく、雨が少ないその村では、水はなにより大切なものだった。
雨水を溜め、ポリタンクに保管してある生ぬるい水ではあったのだが、タイ人のホスピタリテイが、ピューター製の器の中に凝縮されていた。
タイ人の村に比べて、マレー人のイスラム教徒の集落には明るさというものがない。圧倒的な仏教徒の社会の中で、マイナリティとして迫害されてきた歴史のせいなのか、あるいは、イスラム教徒に特有の、宗教的な優越感や排他主義から来るものなのだろうか。異教徒の闖入者を見つめる眼差しは、冷ややかだ。
村長のおおげさな笑顔の下にある醒めた感情に、スワンニーはもちろん気づいている。彼らは愚かでもなければ、お人よしでもない。甘い言葉だけでは、一センチも釣り上げることはできないだろう。
村は、そのまま海に面していた。村人たちは、ここから出漁するのだ。砂浜に敷いたゴザの上に、魚の干物が干してある。このあたりの風景は、日本の漁村と大差はない。
漁村のはずれから、南の方角に向かって、数キロに渡り砂浜が続いている。砂浜の背後では、丈の高い松林が白いビーチに影を落としている。スワンニーは、ここをリゾート・ビーチとして開発したいのだろう。そのために、道路や電気などの基盤整備が不可欠なのだ。
村の広場に帰る途中、小道に面した作業小屋の中で、信也は、意外な人物を見かけた。一人の若者が、ルア・ハン・ヤオと呼ばれるできたてのロング・テール・ボートに色を塗っている。龍をモチーフにしたサイケデリックなデザインで、趣味は悪いし、けばけばしいのだが、絵を描いている本人は誇らしげだった。
その若者の横顔に、信也は思い当たった。スワンニーの秘書、カトレヤの後を追ってソンクラーへ行ったときのことだ。スワンニーの別邸の前で擦れ違ったマレー人の若者が、いま、彼の目の前で、手作りの木造ボートに、最後の仕上げをしていた。
メール トップ